アノテーションのその先を見据えて
富士ソフト株式会社
2025年 5月13日
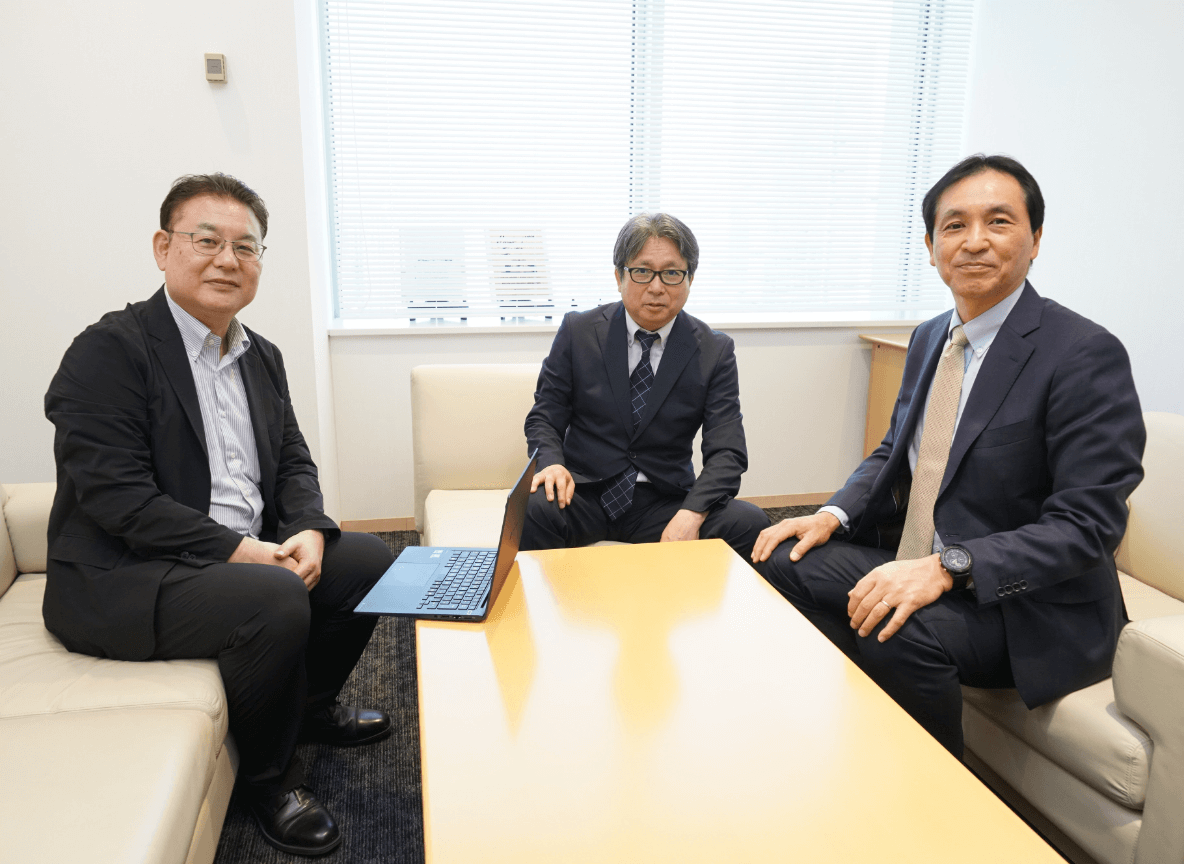
生藤 TTピーエム株式会社(以下、TTPM)創立40周年ということで、日本システム技術株式会社(以下、JAST)の澤田サービスセンター長にお話をお伺いします。
澤田様 40周年おめでとうございます。
木山 最初にJAST様のご紹介をお願いします。
澤田様 弊社はシステム受託開発をメインとする独立系SIerで、2023年に50周年を迎えました。2009年頃にレセプト点検システムの開発を始め、今の医療ビックデータ事業の基盤となるサービス提供を開始しました。その事業の中では「JMICS(ジェイミクス)」および「iBss(アイビス)」といったシステムを提供し、保険者業務の効率化や付帯業務のアウトソーシング化を支援しています。現在では、保健事業のみならず、給付適用に至るまでワンストップでサービス提供できます。
事業理念として、「健康寿命の延伸」、および「国民皆保険制度の維持」を掲げ、業務に邁進しています。
木山 ありがとうございます。健保業界は厳しい状況が続いています。その中でJAST様としてのヘルスケアサービスの役割はどのように捉えていらっしゃいますか。
澤田様 大きな命題としては、医療費の削減が使命だと考えています。事業の始まりがレセプト点検のみでしたが、その後レセプトデータを分析し、通知やデータレポートを通じて医療費の適正化に貢献してきました。そこから「iBss」へと発展し、健保様の業務効率化をDXで支援しています。
BPO事業では2020年から「iBss」活用による被扶養者資格調査のWeb化を開始しました。コロナ禍もあって紙からWebへの移行が進み、当初16健保だった導入数は、現在その10倍にまで増えています。
一方で、競合他社が「iBss」を解析して似たようなシステムをリリースするなど、楽観視できる状態ではありません。もうひとつ、中間サーバーを介して健保様が前年度の収入情報などを取得できるため、これまで審査対象としていた無収入の方を対象外にされるなど、審査対象の件数が大幅に絞られるケースも増えており、無視できない状況になりつつあります。
木山 事業環境の変化についてはいかがでしょうか。
澤田様 BPO事業についてお話しますと、派遣スタッフの人件費が高騰していることは注視しています。BPO業務は人的作業が必須となるので、そこはネックになっています。そうした状況に対して、昨年度からAIボイスボットを導入しました。コールセンターでAIが一次受けする仕組みを導入し、オペレーターまでつながる割合は約50%減少しました。これについてはかなり効率化できたと思います。
2025年度はメール問い合わせの返信や、電話の内容の文字起こしから問い合わせの要約などにも生成AIを活用し始めており、なるべく人の作業量を減らしながら多くの業務が受けられるように進めています。
生藤社長 なるほど、システム開発で培った技術力を活用しているわけですね。
木山 そうした中で、被扶養者資格調査業務、第三者行為求償業務を受託させていただいていますが、TTPMに対する評価や今後の期待をお聞かせください。
澤田様 2024年度から委託を開始し、当社としても外部委託は初めてだったこともあり、初期はコミュニケーションに課題もあったと認識しています。今年度はコミュニケーションのレベルを上げたところからスタートできるといいのかなと考えています。また被扶養者資格調査業務は、完遂できて当たり前とされているものであり、お客様の要求水準が高いためよりスピードと精度をあげた対応をお願いします。
一方で、第三者行為求償業務は順調と聞いています。こちらは今のペースで継続いただければと思います。
生藤社長 反省すべき点は反省し、厳しいお声はご期待の裏返しと捉えて精進していきます。
木山 先ほど、人材不足というお話もありましたが、その領域で一緒に取り組めそうなことはあるでしょうか。
澤田様 被扶養者資格調査業務の漸減に合わせ、「iBss」には新たにWeb申請の機能や支給決定通知機能などを追加実装して、これまで紙でやりとりしていたものをWeb化する開発をすすめているところです。その中でBPOとしてできるところもサービスとして開発していく考えです。
補助金申請や医療費通知も「iBss」のWeb上で完結することが可能ですし、ウォーキングアプリと連携して、歩数でランキングが表示されたり、ポイントを貯めて金券等と交換できる仕組みもシステムとしてはできています。「iBss」の利用がもう少し広がれば、健保様にとっても加入者と直接つながるプラットフォームになっていけると思っています。これまで冊子などでお知らせしていたことも、全部デジタルで届けられるようになれば、情報発信のあり方も変わっていくはずで、さらにいろいろな協業の可能性が出てくると考えています。
生藤社長 健保様の業務をどう効率化してあげるかということですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
